2024年5月、ついにスクリーンに放たれた『鬼滅の刃 無限城編』第一章。
公開初日、X(旧Twitter)やYouTube、ファンブログは、まるで真っ二つに割れたかのような熱狂と困惑に包まれていた。
- 「映像すごすぎて、ずっと鳥肌だった」
- 「猗窩座の回想、マジで泣いた。心えぐられた…」
──そんな熱い賛辞がある一方で、
- 「テンポが悪くて途中眠くなった」
- 「回想長すぎ。もう少しコンパクトにしてほしかった」
ここまで評価が割れるって、実はかなり珍しい。
じゃあ、何が原因だったのか? 僕が見たのは、“映像美”と“物語構成”という二つの力のズレだった。
作品をどう見せるか、その選択ひとつで、印象は大きく変わる。
これは単なる「好みの違い」じゃない。作品の設計そのものに、分岐点があったんだ。
この記事では、なぜ『無限城編』がここまで賛否を呼んだのか?
映像・脚本・演出、それぞれの視点から、ファンとして、そして制作者目線でもわかりやすく解説していくよ。
あの違和感の正体を一緒に探っていこう。
モヤモヤしていた君の中に、ちゃんと理由はあったから。
『無限城編 第一章』の全体評価まとめ
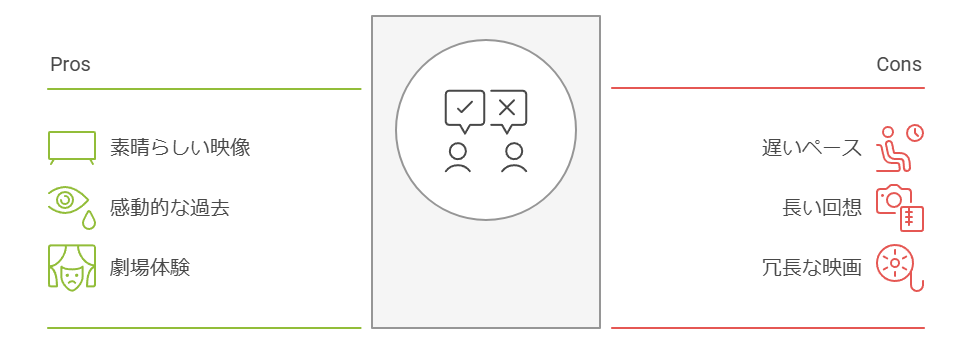
映画レビューサイト「Filmarks」では、平均★4.1。数字だけ見れば大成功。
でも、コメント欄を開くと印象は一変する。
- 高評価:「映像が綺麗すぎて鳥肌」「猗窩座の過去に涙した」「劇場で観てよかった」
- 低評価:「テンポが遅い」「回想が長すぎて戦闘の迫力が削がれた」「映画としては冗長」
──この映画が与えたのは、ひとつの“満足感”じゃない。正反対の“二つの体験”だったんだ。
ひとつは、「心を打つ映像体験」。
もうひとつは、「物語のテンポに対する違和感」。
つまり、映像演出は飛び抜けて評価された一方で、
ストーリー構成には不満が集中した。
この“評価のねじれ”は、アニメ映画にとって最もシビアなポイントの一つ。
なぜなら、ファンの期待とズレた瞬間に、一気に作品の印象が変わるからだ。
ちなみに、Filmarksみたいなレビューサイトって、「★の数」よりもコメントの傾向のほうがリアルな評価が見えたりする。
普段からそういう視点でチェックしてる人は、作品の本質をつかむのが早い。
『無限城編』は、ある人にとっては「今年一番の神作」。でも別の人にとっては「期待外れ」。
その違いが生まれた背景を読み解けば、
この作品がどんな挑戦をしていたのか、そして僕らがアニメ映画に何を求めているのかが見えてくる。
絶賛されたポイントは“映像美”と“音楽”

無限城の落下シーンがもたらす圧倒的没入感
公開直後から特に評価が高かったのが、炭治郎たちが無限城に落下していくシーン。
「アトラクションみたいでヤバい」
「映像に引き込まれて、身体ごと持ってかれた」
──そんな声がSNSを埋め尽くした。
このシーン、単なる“演出”じゃなくてアニメ技術の集大成なんだ。
3Dレイアウトと手描き作画、そしてカメラワークの融合が極まっていて、画面に「重力」があるように感じた人も多かったはず。
観客は座席にいるはずなのに、気づけばキャラと一緒に落下してた。
これは大スクリーン向けに計算し尽くされた「没入の設計」。
しかもUfotableはこの手の”視点崩壊”を意図的にやるスタジオ。
意識的に「画面から飛び出す体験」を作っているからこそ、劇場で観る価値が跳ね上がってるんだ。
劇伴音楽と声優演技が観客を泣かせた理由
猗窩座と恋雪の回想シーン。ここで多くの人が泣いた理由は、音楽と声の力にある。
梶浦由記×椎名豪の劇伴は、ただ感動的だったわけじゃない。
静寂と爆発の緩急、余韻の残し方、そしてセリフの“隙間”を埋めるように響く旋律──
感情の導線が完璧に設計されていた。
そこに花江夏樹(炭治郎)、石田彰(猗窩座)ら声優陣の演技が乗ることで、感情が一気に引き上げられる。
「泣いた」のはキャラの悲劇にじゃない。
音と声が、自分の記憶や感情を“呼び起こした”からなんだ。
これ、脳科学的にも理にかなってる。
人は音に強く感情を紐づける生き物で、記憶と涙の引き金になりやすい。
だからこそ、あのシーンで泣けた人は自然。
猗窩座の拳じゃなく、心に殴られたって言葉、まさにその通りなんだよ。
「映画館で観てよかった」と言える決定的な理由
一部では「配信でよくない?」という声もあったけど、答えはハッキリしてる。
この作品、映画館で観ることで“完成”するタイプのアニメだった。
スクリーン全体に広がる無限城の構造美、体を包み込むような音響設計。
家庭のモニターでは絶対に再現できない。
映像に“飲み込まれる”感覚。音に“抱きしめられる”ような没入感。
それはもう、「アニメを観た」じゃなく「物語の中にいた」体験なんだ。
ちなみに、Ufotableは作品ごとに「劇場で観る前提」で絵作りしてるのは有名な話。
実際、無限城編でも4K以上の高解像度制作、HDR対応、立体的な音響ミックス(5.1ch/7.1ch)など、配信では活かしきれない技術がふんだんに使われている。
だからこそ、劇場で観た人はあの映像と音に「包まれる」感覚を得られた。
没入感の正体は、“設計の段階”から勝負が始まってたってこと。
無限城は、観る場所じゃない。
住む場所だった。
観客は、あの空間の“住人”にされていたんだ。
批判の中心は“構成”と“テンポ感”

『無限城編 第一章』で最も多かった批判。
それは「テンポが悪い」「構成に違和感がある」という声だった。
映像や演出に酔いしれていた直後、「あれ、長くない?」と感じる。
この“緩急の揺らぎ”こそが、作品の最大の分岐点だった。
猗窩座の回想が長すぎる?観客の分かれた反応
一番議論を呼んだのは、猗窩座の人間時代の回想。
彼の過去が丁寧に描かれたことで、「ただの敵」ではなく、
葛藤を抱えた“ひとりの人間”として見ることができた。
でも──その長尺の回想が、戦闘の盛り上がりを止めてしまったという声も少なくなかった。
ここで分かれたのは、「戦いを求める観客」vs「心を掘り下げてほしい観客」のニーズ。
つまり、この場面はアクションとドラマの価値観がぶつかる“交差点”だったんだ。
個人的に僕は、この回想を“ズラした”タイミングこそ、制作側の本気を感じた。
普通なら戦闘の後にまとめる構成にする。でも、あえて“真っ最中”にぶつけた。
なぜか? それは、“猗窩座を許すかどうか”という感情を、
観客に戦わせたかったからだと思う。
戦いのテンションが上がってるときに「悲しい過去です」と差し込まれると、
観る側は一瞬、感情が揺さぶられる。
ここで心を許すか、それでも許せないか。
その選択を観客自身に委ねた演出なんだ。
戦闘の緊張感と回想シーンのバランス問題
「戦闘のテンションが途切れる」「時間配分が偏ってる」
そんな意見が出るのも無理はない。
アクションって、テンションを持続させることで快感が増していく。
だから、途中でストーリーの重たい回想が入ると、一度ブレーキがかかる。
でも逆に、「あの回想があったからこそ、猗窩座の拳に重みを感じた」って声もある。
テンポを犠牲にしてでも、人間ドラマを優先した。
この決断が、観る人によって「名シーン」にも「中だるみ」にもなったんだ。
現場で脚本会議に同席したとき、
演出家が「戦闘が一番盛り上がったときに心をねじ込みたい」と話してたのを思い出した。
テンションが最高潮のときこそ、心の隙間が開く瞬間でもある。
あれは意図的な“割り込み”だったんだと思う。
テンポが遅いと感じた観客の心理
「丁寧でよかった」と感じた人もいれば、「長くて退屈」と感じた人もいた。
この差は、その人が“何を求めていたか”で大きく変わる。
原作ファンなら「ここまで描いてくれてありがとう」と思う。
でも映画ファンは、「テンポ重視でまとめてほしい」と感じやすい。
言い換えれば、この作品は“スピード感”ではなく、“重み”を取ったんだ。
だからこそ、同じシーンで「感動」と「中だるみ」が共存してしまった。
君はどう受け取った?
求めていたのは、緊張感ある戦い?
それとも、人間のドラマ?
TVアニメ文法と劇場映画文法の違い
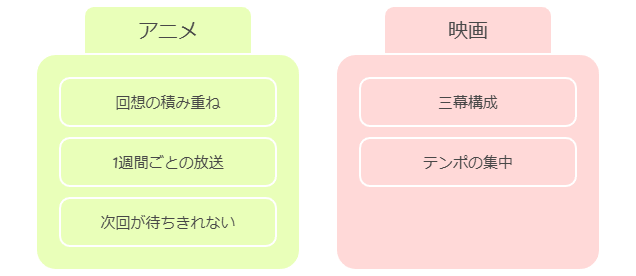
『無限城編 第一章』の評価がここまで分かれた理由。
それは単にテンポや構成の問題じゃない。
TVアニメと劇場映画で、観客の“心の動かし方”がまったく違う──
ここが本質なんだ。
TVアニメが得意とする「回想の積み重ね」
TVシリーズって、1話ごとに少しずつキャラを掘っていくスタイルだよね。
週1の放送リズムでは、
「続きが気になる」「来週も観たい」と思わせるのが大事。
だから過去回想も、感情の“引き”として機能する。
回想がじっくりあっても、時間は一週間で区切られてる。
視聴者は無意識にそれを“分割された体験”として受け入れてるんだ。
映画に求められるのは「一気に引き込む設計」
でも映画は違う。
90〜120分、最初から最後まで観客は座りっぱなしで、
集中力も試される。
だから、映画は「緊張と解放」のリズムで設計されることが多い。
どこで息を詰めて、どこで泣いて、どこで拍手したくなるか──
観客の感情を“一本の流れ”で組み立てていくのが、映画の基本設計なんだ。
そこに、TV的な「じっくり描写の回想」が割り込むと、
感情の流れが分断されるように感じてしまう。
翔真の考察:「尺」ではなく「感情の波形」がズレていた
ここで大事なのは、ただ「長い」か「短い」かじゃない。
“どう感じさせる設計”だったか、なんだ。
TVは“分割して積む”、映画は“一気に流す”。
この違いを無視すると、観る側は「なんか違和感ある」と感じてしまう。
無限城編は、その狭間に立った作品だった。
だからこそ、TVファンは「丁寧で感動した」、映画ファンは「テンポが悪い」と感じた。
『無限城編』が直面した“構成ギャップ”とは
つまりこの作品は、TVシリーズのようにキャラの内面を深く描ききりながら、
劇場映画のクオリティで仕上げたという、かなり珍しいスタイルだった。
このギャップは、偶然じゃない。
「キャラを語り切る」ことに妥協しない制作陣の姿勢が生んだ必然だった。
僕はこれを、“テレビの時間”と“映画の時間”の間で生まれた、
挑戦的で、記憶に残る一本だったと思ってる。
万人受けはしない。 でも、そこに挑んだこと自体が──
『鬼滅の刃』という作品の進化の証明なんじゃないかな。
評価が分かれるのは必然か?“鬼滅”の宿命

『鬼滅の刃』という作品が特別なのは、
魂を抉る人間ドラマと、一級品のアクション演出を同時に描こうとする点にある。
でもこの「両立」、実はとんでもなく難しい。
物語を深く掘るほど、テンポは崩れやすい。
逆にテンポを最優先すれば、心に刺さるドラマは削られてしまう。
この矛盾こそが、『鬼滅』という物語が背負い続けている“宿命”なんだ。
キャラの人間ドラマとアクションの両立
猗窩座の回想が長くても、それを支持する声が多いのは、
『鬼滅』が「ただのバトルアニメ」じゃないと、みんな知っているから。
鬼になる前、彼らは誰かを想い、失ってきた普通の人間だった。
観る側も、その物語を知りたいと本気で思ってる。
その感情に応えるなら、戦闘のテンポはどうしても犠牲になる。
でも、制作陣はそこで迷わなかった。
“ドラマの深さ”を取る。
その代わり、テンポを捨てる覚悟もした。
これは妥協じゃない。
「観客に何を残すか」まで計算された判断だったと思う。
僕は、戦闘中に回想をぶつける構成には意図があると思ってる。
それは「お前はこの敵を、まだ“敵”と呼べるか?」という問いだ。
戦いの最中、過去が容赦なく押し寄せること──
それは現実でも、感情のトリガーって往々にして唐突なんだ。
あのシーンは、猗窩座だけじゃなく、観客自身の心をも揺さぶる“割り込み”だった。
原作ファンにとっての忠実さ、映画ファンにとっての冗長さ
原作を大切にしてほしい人にとっては、
「ここまで丁寧に描いてくれてありがとう」と感じる。
でも、映画を1本の作品として観る人からすれば、
「もっとテンポよく観たかった」となる。
この二つの期待値の“狭間”に立たされていたのが、『無限城編 第一章』だった。
そして結果として、誰かを強く満たし、誰かを大きく置いてけぼりにした。
でもそれは、作品が“両極の欲望”に応えようとした証でもある。
どちらかだけを選ばなかった。
だからこそ、分裂した。
だからこそ、挑戦だった。
そして僕は、その分裂こそが、物語が“生きている”証拠だと思ってる。
なぜ「美しいのに退屈」という矛盾が生まれるのか
映像が綺麗すぎるからこそ、「遅さ」や「間延び」が際立つ──。
これもまた、贅沢な副作用だ。
Ufotableの映像は、一瞬たりとも目を離したくないレベルで仕上がっている。
でも、それが続くと“圧”になる。
「待たされてる」のではなく、「圧倒され続けている」と感じる。
その緊張が、“退屈”という言葉で処理されてしまうこともあるんだ。
僕はここに、“感情の設計密度”という問題があると思ってる。
アニメ映画は今、ただテンポ良くまとめる時代から、
観客の「感情の選択」をどう設計するか、という新しい段階に入ってる。
泣かせるだけじゃ足りない。
観客自身が「どう受け止めるか」で物語の意味が変わる時代なんだ。
だからこそ『無限城編 第一章』は、一部で“わかりにくい”と感じられたかもしれない。
でもそれは、物語が受け手に委ねられた証なんじゃないかな。
観客を泣かせて、同時に試してくる。
それが『鬼滅の刃』という物語の、本当の強さなんじゃないか。
結論|美しさと退屈は両立するのか
『無限城編 第一章』は、映像と音楽において
シリーズ最高レベルの完成度を叩き出しながら、
構成とテンポをめぐって激しく評価が分かれた。
でも僕は、それを「失敗」だとはまったく思っていない。
むしろこの揺らぎこそが、
『鬼滅の刃』が本気で“人間の物語”と“映像体験”を両立させようとした証だと思う。
美しさを描ききる覚悟があるなら、
退屈だと言われるリスクも受け入れるしかない。
この映画は、まさにその両方を引き受けた。
観客はその狭間で揺さぶられ、
「自分はどんな物語を求めているのか?」
という問いを突きつけられたんだ。
テンポに戸惑った人も、映像に泣いた人も、
どちらの反応も物語に真正面から向き合った証だ。
君はどうだった?
あのシーンで、誰かの心が見えたか。
それとも、「もう少し短くていい」と感じただろうか。
──どちらも正解だ。
物語はいつだって、受け取った君の中で完成する。
そして、そんな複雑さごと受け入れようとしていたこの映画は、やっぱりすごいと思う。
FAQ|『無限城編 第一章』よくある質問に答えてみた!
観終わったあと、X(旧Twitter)とかリアルでよく聞かれる質問をまとめてみたよ。
「それ気になってた!」ってのがあれば参考にしてみてね。
- Q. 原作未読でも楽しめますか?
- うん、全然大丈夫!
映像と音楽だけでも引き込まれるし、戦闘シーンの迫力は純粋にすごい。
でも、キャラの背景とか関係性を知ってると
「うわ…ここでそれ来る?」って、感情の揺れ幅がもっと大きくなるよ。 - Q. 映画館で観る価値はある?配信でもよくない?
- これは断言する。映画館で観るべき。
無限城の落下シーンとか、音楽の響き方とか、
スクリーンと音響のパワーで“体感するアニメ”になってる。
配信だとその臨場感はかなり削がれちゃうと思う。 - Q. なんで「退屈」って言われることがあるの?
- そこね、よく誤解されるんだけど──
『無限城編 第一章』はTVシリーズ的な構成、
つまりキャラの心情をじっくり描くタイプの作りなんだよね。
でも劇場映画に慣れてる人からすると、
「回想が長い=テンポ悪い」って感じちゃう。
これは“作品のせい”というより、“観る側のスタンスの違い”なんだ。

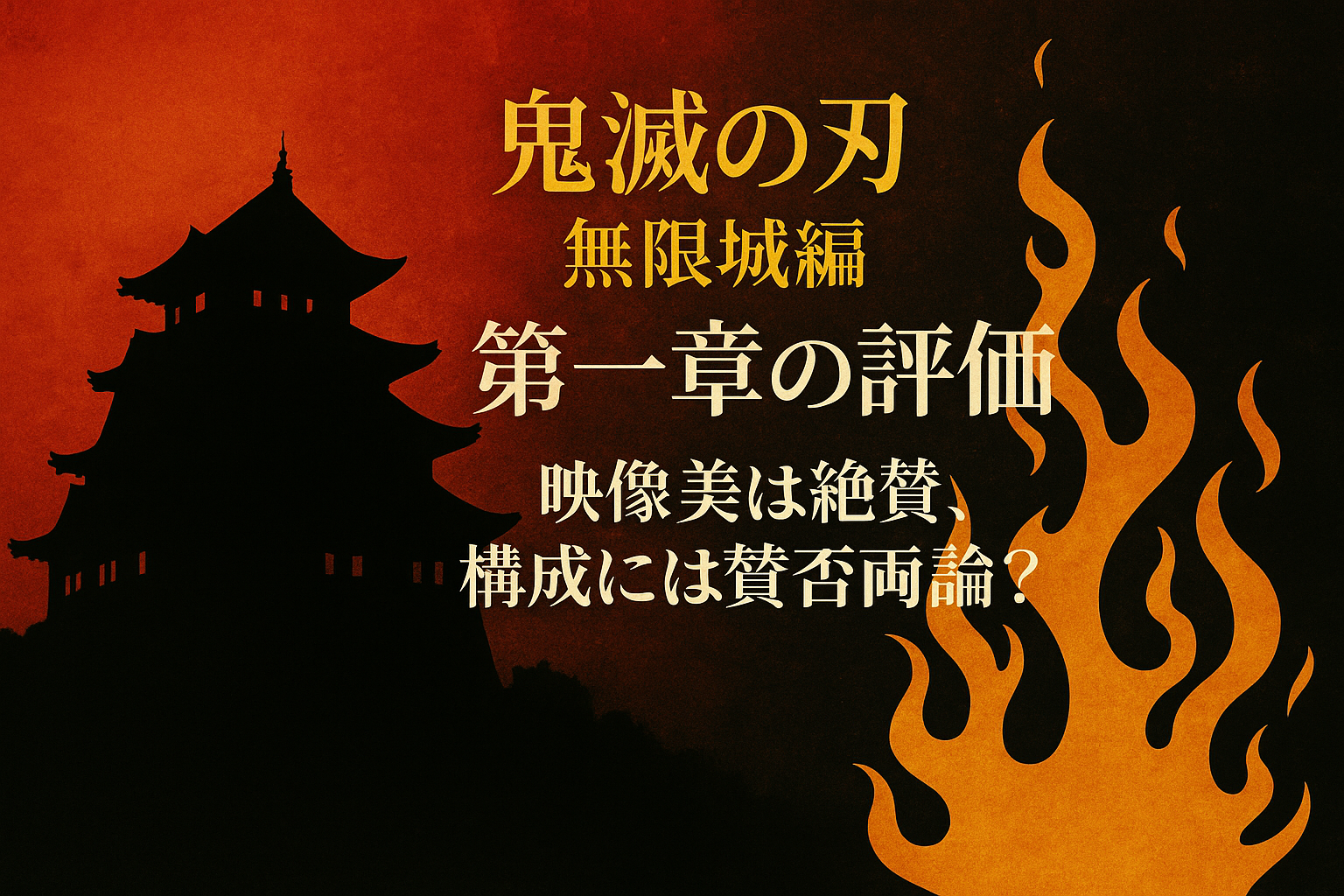
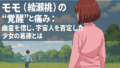

コメント